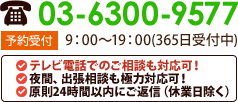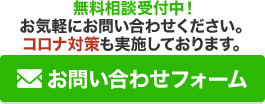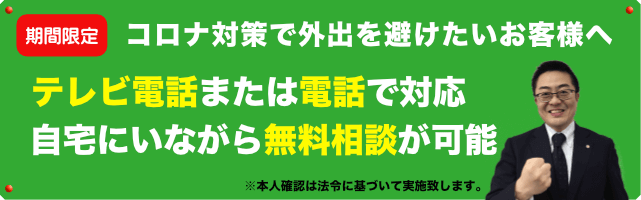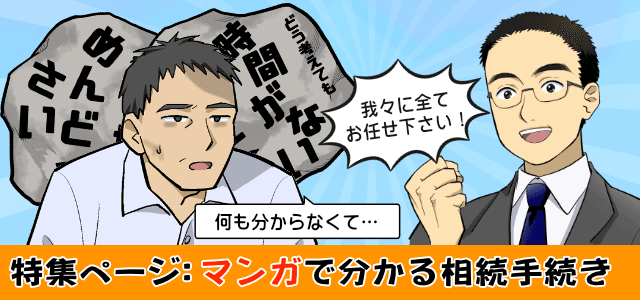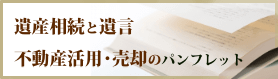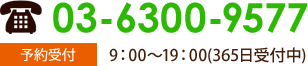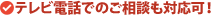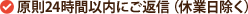税制改正によって創設された新・事業承継税制に注目が集まっていますが、事業承継は税制に注意するだけではうまくいきません。事業承継に際しては、税制面に加えて、ビジネス面、法制面、金融面の4つの視点からの総合的アプローチが重要だと考えています。
事業承継成功のために② 事業承継は、4つの視点に留意する必要がある
事業承継の4つの視点
<ビジネス面>
ビジネス面は最も重要です。税制は株式の移転時点における価値課税問題ですが、事業は過去から未来に脈々と継続していく線として捉える必要があります。事業承継の対象となる事業価値の源泉は何か?また、その価値は誰に帰属しているのか? などを把握し、事業価値の源泉を前提として承継するための仕組みづくりや環境づくりなどの課題を洗い出し、ひとつひとつ解決策を考え、対応策を講じるのが承継計画です。この承継計画に沿って、事業承継を進めるのが基本です。
事業承継の方法として親族内承継がメジャーです。しかし、それが難しい場合には、役員や従業員への承継、M&Aによる売却を検討することになります。
<法制面>
法制面は他の親族との間の遺留分問題や経営者・後継者の調整の場面などで重要となります。特に、遺留分問題は後継者に兄弟姉妹がいる場合、大きな問題になる恐れがあります。事業承継は承継計画に基づき、後継者に自社株を承継してもらうように進めていかなければいけません。
ただし、自社株も相続発生時には相続財産とみなされますので、遺産分割時に遺留分の計算の中に含まれてしまいます。後継者以外の相続人に遺留分を主張され、後継者以外に自社株が渡ってしまっては当初の目的が達成されません。その事前対策として民法には『事前に自社株評価を固定して遺留分に含める特例』や『事前に自社株評価を固定しないが遺留分には含めない特例』などがあります。どちらの特例にもメリット・デメリットがありますので、検討する場合は専門家に相談することが重要です。
<金融面>
金融面は、従業員や役員に承継してもらう場合の株式買取り資金の調達問題、経営者保証の引継ぎ問題などがあります。
<税制面>
税制面は、新・事業承継税制が中心になりますが、一方で株価対策を無視するわけにはいきません。事後要件(贈与・相続後も遵守すべき要件)に抵触して猶予された税金の納付が発生した場合や、相続税の計算方法の問題(相続税は累進課税で計算されるため、株価が高いと株式以外の税額が増加する)などがあり、株価はできるだけ安くしておいた方が有利です。
以上の4つの視点は、事業承継に際して非常に重要です。また、事業承継計画を作成する上でも考慮が必要となります。
2018年5月30日に国土交通省が発表した『平成29年度住宅市場動向調査』によると、土地を購入した注文住宅新築世帯の平均購入資金は4,334万円でした。 なお、住宅を購入するにあたり、子や孫へ住宅購入費用を援助することもあるでしょう。そこで活用できるのが『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』と『相続時精算課税制度』です。今回は、2つの制度の違いや注意点についてご紹介します。
子や孫への住宅資金贈与 利用したい2つの非課税制度と注意点
『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』とは?
父母や祖父母などの直系親族から、自宅の新築または増改築などにあてるための資金を贈与された際に、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
なお、『暦年贈与』(※1)や『相続時精算課税制度』と併用して活用することもできます。さらに相続開始前3年以内に住宅取得等資金の贈与があったとしても、相続財産には加算されません。
『相続時精算課税制度』とは?
60歳以上の直系尊属から贈与を受けた場合に、2,500万円まで贈与税を非課税に、2,500万円を超えた分の20%に贈与税が課税される制度です。『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』と併用できるなど一見メリットが大きいように思えますが、節税対策として活用する際には以下の点に注意する必要があります。

【注意点1】
仮に2,000万円を子どもに贈与した場合、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税は課税されません。しかし、相続時には贈与時の評価額2,000万円が相続財産に組み込まれ、相続税課税対象となってしまいます。
【注意点2】
相続時精算課税制度を一度利用すると、同一贈与者からの生前贈与に対して『暦年贈与』を利用することはできません。ただし、贈与者が異なる場合は『暦年贈与』を活用できます。
【注意点3】
『小規模宅地の特例』(※2)との併用もできません。仮に、評価額1億円の自宅の土地が小規模宅地に当たる場合、要件が揃えば相続税の評価額を2,000万円まで下げられることもあります。しかし、相続時精算課税制度を利用すると、1億円が課税対象額となり、贈与税額は(1億円-2,500万円)×20%=1,500万円となります。
後々「贈与税は非課税となったけど、相続税で課税された!」ということにならないよう、非課税制度のリスクをしっかり確認しておくことが大切です。
なお、『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』と『相続時精算課税制度』を適用するには、必ず申告する 必要があるので注意しましょう。
※1 毎年一定額(1人あたり年間110万円)までの贈与であれば非課税となる制度。ただし、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与には相続税がかかります。
※2 一定の要件を満たした場合、亡くなった人が自宅として使用していた330㎡までの土地を8割引きで相続できる制度。
平成30年度の税制改正によって何が変わった? その1
平成30年度の税制改正により、相続税や贈与税の特例条件が『緩和されたもの』『厳しくなったもの』『規制されたもの』があります。そのため、今回から2回にわたり、条件が変更となった6つの制度を取り上げ、変更点をお伝えします。
(1)家なき子特例の適用条件が 厳しく
小規模宅地の特例は、賃貸や社宅に住む親族も対象となるため、自宅を子や孫、会社名義にして特例を受けることもできました。
しかし、平成30年度の税制改正により、以下『相続開始前3年以内に3親等の親族等が所有する家屋に居住したことがある者』、または『相続対象の家屋を過去に所有していたことがある者』は対象外となったのです。
(2)一般社団法人課税の見直し
一般社団法人は、設立が簡単な上、役員の人数や親族の割合の制限もありません。また、非営利型一般社団法人の保有財産は相続税の対象外となるため、役員を親族で固めて法人に財産を移すことで、相続税や贈与税を大きく節税することが可能でした。しかし、平成30年度の税制改正では、特定一般社団法人等(※1)に該当する場合、当該社団法人に相続税が課税されることになりま
した。
(3)農地等の納税猶予の特例見直し
生産緑地は2022年の転用制限解除による宅地用土地の過剰供給が問題視されています。これを受け、平成30年度の税制改正において、主に以下の点が変更となりました。
●三大都市圏の特定市以外は、営農継続要件が20年から終身へ
●買取申出が10年先延ばしにできる特定生産緑地の範囲を拡大
●貸付された生産緑地も納税猶予の対象へ
今回は、以上の3制度について変更点をご紹介しました。次回も平成30年度の税制改正による、特例制度などの条件変更をお伝えします。
※1 相続開始直前の時点で、同族役員が全役員の2分の1超、または相続開始前の5年間で同族役員が全役員の2分の1を超えている状態が3年以上の場合。